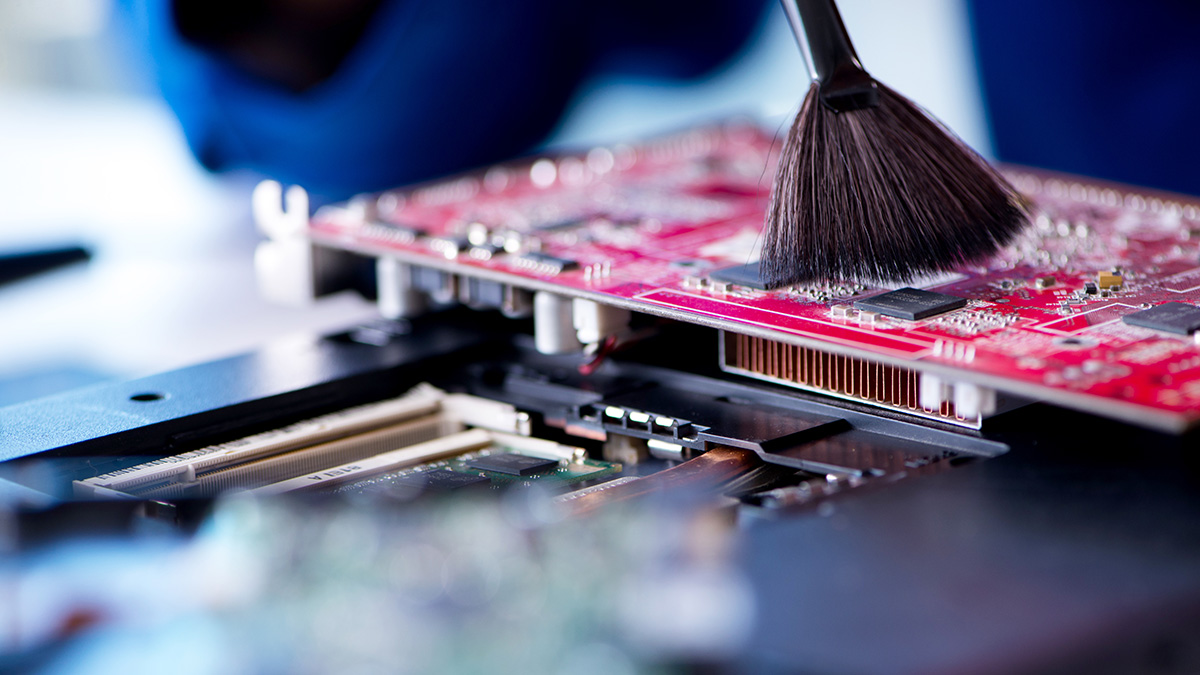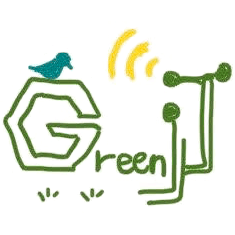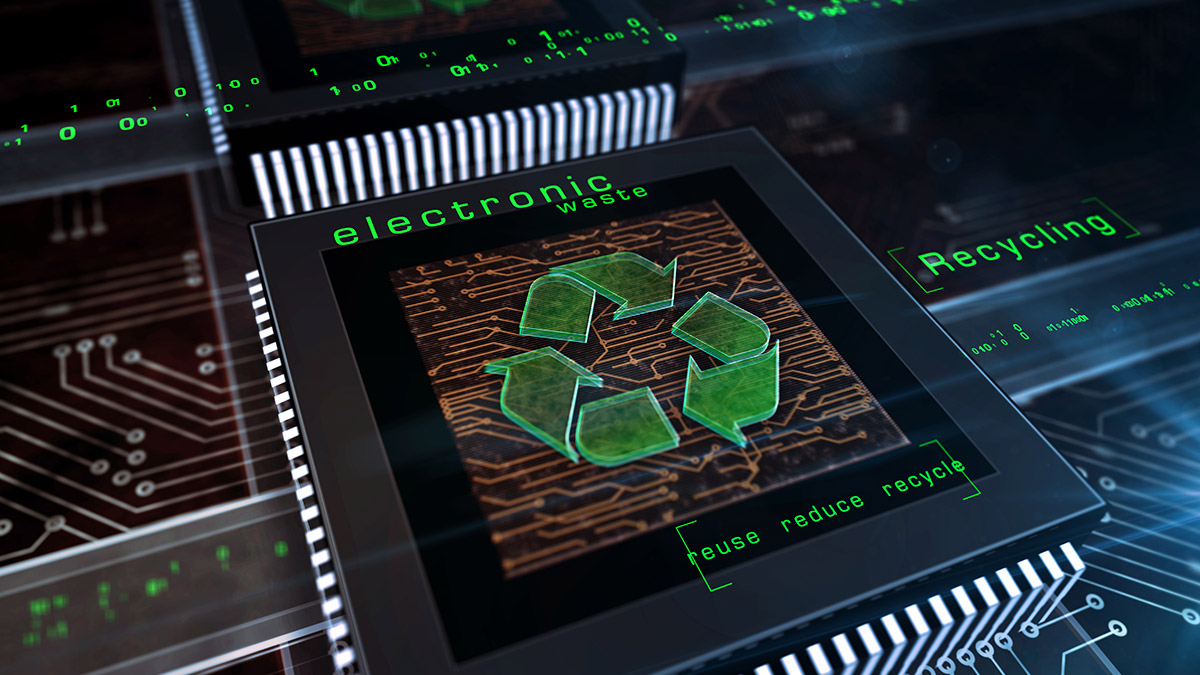英国の造幣局から教育機関・企業までがリユースPCを活用
2022年9月、英国の硬貨製造を担う王立造幣局(The Royal Mint)は、サステナブルな運営を行うための施策の一環として、約70台のリユースPCを導入しました(*1)。ブリストル市議会は、脱炭素を目指し、数年前から市議会でリユースPCを使用しています(*2)。教育機関でも取り組みが進められており、チチェスター高校では114台のリユースPCを採用しました(*3)。 企業の中では、インフラ関連企業であるBalfour Beatty社が、リユースPCを 5,700台購入し、使用しています(*4)。
実現の背景にあるのは、専門企業が築いた信頼と、ステークホルダーの環境意識の高まり
なぜ、こんなに多くの事例があるのでしょうか? 導入がスムーズにできた背景には使用済みのPCを再整備し、リユースPCとして販売をしているCircular Computing社が築いてきた信頼と、ステークホルダーの環境意識の高まりがあります。
2017年に設立されたCircular Computing社は、前述した事例のリユースPCをすべて提供している、英国のポーツマスにある企業です。新製品と比べても遜色がない質のリユースPCを提供することを信条としており、「中古=壊れやすい」というイメージを払しょくすることに成功しました。高品質で低価格なリユースPCの提供を実現し、英国を中心に売り上げを伸ばし続けています。
同社は、信頼を築くために企業努力を重ねています。2021年には、リユースPCとして初めて、製品が適切に製造されていることを証明する国際規格「BSI Kitemark」の認証を取得しました(*5)。また、消費者が中古を避ける理由の一つである「壊れるのではないか」という不安に対処するため、3年の製品保証を付けています。製品としての機能性も高く、返品保証(Return Merchandise Authorization:RMA)で返品された製品は3%以下と発表されています(*6)。同社のリユースPCを導入した高校の担当者からは「普段の感覚で思い浮かべる『中古』とは一線を画す、新品同様の製品でした。あまりにも良かったので地域の学校運営を担っているTKATマルチアカデミートラストにも勧めました」というコメントが寄せられています(*3)。
組織・企業側がリユースPCを導入する後押しになっているのは、環境意識の高い、株主や消費者等のステークホルダーからの「ESGに対応してほしい」「環境負荷を低くしてほしい」といった要望です。こうした声に対しCircular Computing社は、リユースPCを選ぶことで、どれくらいのCO2を削減できるか、節水に貢献できるかを明記し、伝えています。また、同社はアフリカ、インド、米国の植林プロジェクトと協働しながら、リユースPC1台の生産につき5本の木を植えています。そのため、組織はリユースPCを選ぶことによる効果を、具体的な数字とともにサステナビリティ報告書やウェブサイトに記すことができます(*7)。
英国での盛り上がりを受け、その他の国でもリユースIT機器の活用が広がりつつあります。台湾のデジタル機器メーカーAcer(エイサー)や、米国生まれのメーカーDELLは、すでに自社のリユースPCを組織にまとめて販売する体制を整えています。
発展のカギは、リユース業者とメーカーの協業

かつてリユース業者は、新品を販売したいメーカーから販売を妨げる存在だと捉えられてきました。しかし、製造に必要な資源に限りがあることが明白になった今、すでにあるものを上手に活用していくことは組織、企業、そして社会全体の課題です。リユース業者とメーカーが協力しあえば、再利用がさらに増え、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現がぐんと近くなります。
日本でも今、リユースの市場規模が拡大しています。英国のように、組織でリユースPCを活用するのが当たり前になる日は、そう遠くないかもしれません。