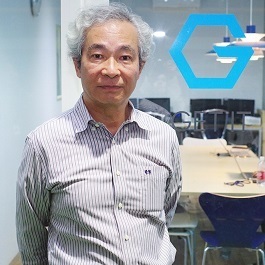現在、コンピュータと呼ばれるシステムに使われている記憶装置の代表格は、ハードディスクドライブ(HDD)であるといっても過言ではありません。近年ではSSDの大容量化や低価格化が進んでいますが、エンタープライズ領域での記憶媒体としてはまだHDDが主役であると言えるでしょう。今日は、そのHDDの発展の歴史を振り返ってみたいと思います。
1.HDDの起源
HDDは、1956年にIBMから発表された、1トン以上もの重量を持った巨大な記憶装置、“IBM RAMAC 305(RAMAC:Random Access Method of Accounting and Controlの略)”から始まりました。記憶媒体として磁気材料が塗布された円盤を使用することで、ランダムアクセス(書き込まれた位置・順番などとは無関係に自由にアクセスできること)が可能になったことが特徴です。現在のような基本の形(プラッタの回転によって発生する気流を利用し、円盤から浮上した状態で情報の読み書きを行い、プラッタの記録面毎に専用のヘッドを持つ)は、1961年に発売された、IBM 1301ディスク記憶装置(IBM 1301 Disk Storage Unit)によって実現されました。
パソコンにHDDが使われるようになったのは、1980年にSeagateがその当時使われていた5.25”フロッピーディスクドライブ(FDD)と同じ外形寸法で、記憶容量5MBのHDD、“ST-506”を発表したことが始まりです。1990年頃までは、この製品の接続I/Fが“ST506”と呼ばれてパソコン用HDDの標準となっていました(※1)。
2.HDDの製造メーカ
現在、HDDメーカは、Seagate、Western Digital(WD)、東芝の3社(HGSTは、WDのブランド名)だけとなっています。ほんの暫く前まで存在した企業も、SAMSUNG(韓国)を除いてHGST(日立・IBM)、Maxtor、Quantumなどアメリカ企業が中心でした。1980年~1990年代初期のHDDの技術開発が盛んであった頃には、日本企業の日立、東芝、富士通、NEC、松下寿電子、富士電機、アルプス電気、エプソン、日本ビクター(JVC)やワイ・イー・データなども製造販売をしていましたが、日立、東芝、富士通を除いて短期間で事業参入を断念してしまいました(※2)。
一方、HDD用の部品は、スピンドルモータ、プラッタなど中心的な性格を持つものまで、今でも日本企業が独占的に製造しているものが多い状態となっています。HDDは「ジャンボジェット機が高度1mm以下で飛んでいる状態」と例えられるように非常に精密に出来ている製品です。なぜHDDに限ってアメリカ企業が中心に製造しているのか、精密工業は日本のお家芸のはずではないか、と疑問に思う方も多いと思いますが、HDDに限ってその原理が成立しなかった理由は、過度に要求される精密度にあります。
日本企業の一般的な設計・品質管理の手法は、各部品の製造上の精度として、許容誤差の最大値を積み上げても完成品が規格内に納まることを要求することが多いのですが、HDDの場合は通常よりもさらに上の精度を要求されるため、部品単体レベルでの設計要求精度で個別の部品を作ろうとすると加工費が高額になりすぎてしまいます。一方、“そこそこ”の精度で作った部品を使って組み立て、組み立てられた完成品が許容範囲に収まらない場合は、完全に元の部品レベルまで分解して、再度組み立て工程に投入し、部品同士の組み合わせによって出来上がった製品の結果で合否を判断する手法をとったアメリカ企業とは、価格競争で勝つことができませんでした。
この手法は、複数の部品を組み立てた場合の総合的な誤差を求めるために品質管理や確率計算で用いられる、「正規分布と二乗平均平方根」の考え方に従ったものということができます。
3.HDDの名称
HDDとは、円盤型磁気記憶装置として同時期に開発・製造されていたFDD(可撓性〔かとうせい:曲げたわめることが出来る〕ディスクドライブ)とはっきり区別するためにつけられた呼び方で、RDD(Rigid Disk Drive:リジッド〔硬質〕ディスクドライブ)や、IBMの開発コード名の「ウインチェスター・ディスク(Winchester Disk)」とも呼ばれていました。現在では完全にHDDと呼ばれるようになり、その他の名称で呼ばれていたことを知っている人は、その頃の時代を生きていた人たちだけであるとも言えるでしょう。
※2: 現在外付けHDDなどを販売している、バッファロー、アイ・オー・データ、ロジテックなどは、HDDを部品として購入し、自社の外付け用HDDやNASと呼ばれる製品に組み込んでいるだけであり、HDDを製造している訳ではない
【著作権は、沼田理氏に帰属します】