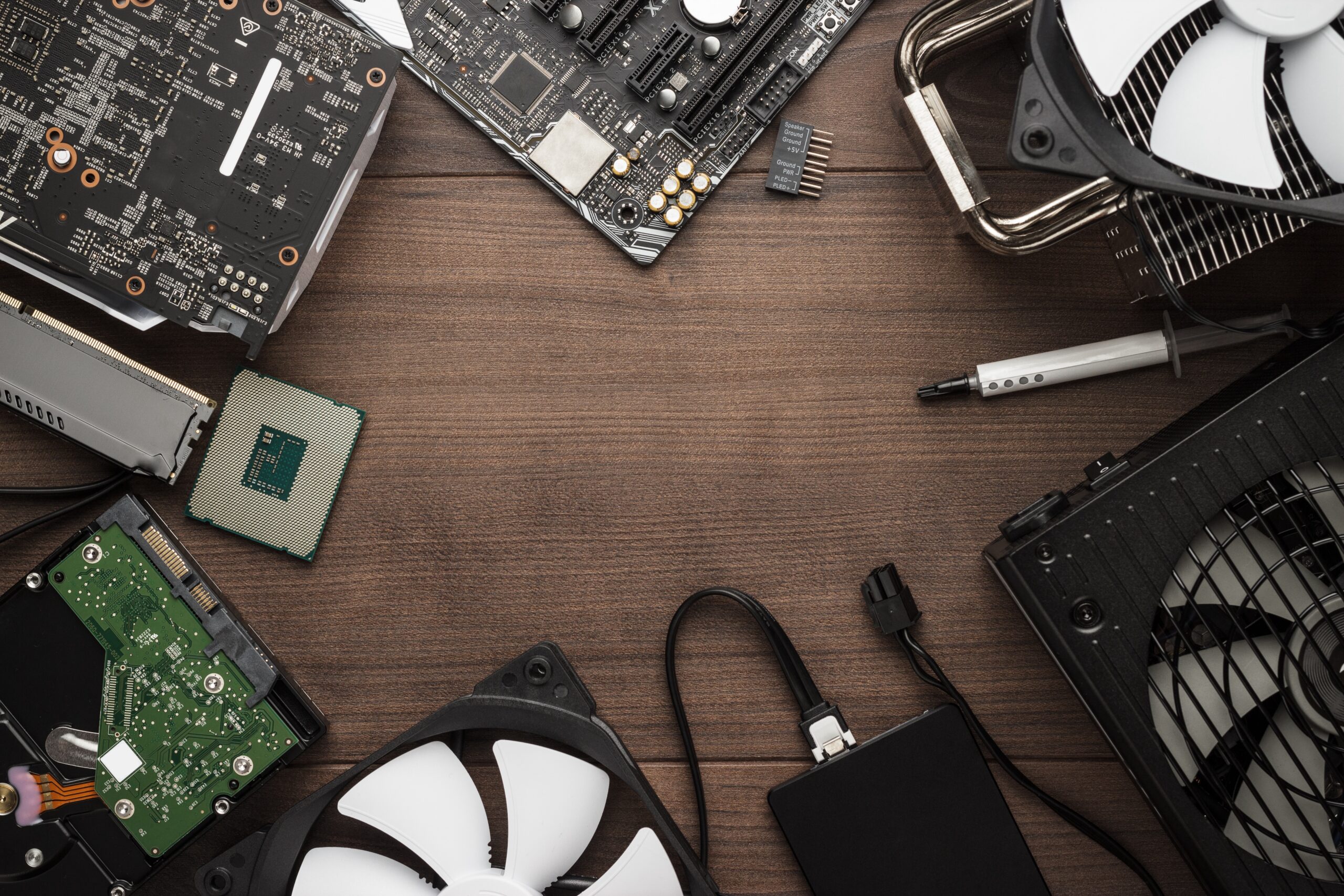
老朽化や性能不足、メーカー保守の終了(EOSL)、さらにはクラウド移行やセキュリティ対策といった経営的・技術的要因により、既存のサーバーやストレージの見直しを検討されている情シスご担当者さまや、IT関連の意思決定に関わるご担当者さまも多いのではないでしょうか。リプレース(リプレイス)の必要性を感じつつも、予算や稟議、業務への影響といったさまざまな制約から、すぐに着手できずにお困りの方も少なくありません。
本記事では、「リプレースとは何か?」という基本的な概念から、代表的な移行方式や、第三者保守といった柔軟な代替策まで、実務に即した視点でわかりやすくご紹介いたします。
リプレース(リプレイス)とは?

リプレースとは、現在稼働しているシステムやIT機器を、新たな機器・構成・サービスに置き換える取り組みのことを指します。リプレースの目的は多岐にわたり、ハードウェアの老朽化や性能限界への対応だけでなく、セキュリティの強化、運用効率の向上、新技術の導入、事業継続計画(BCP)の見直しなど、企業のIT戦略全体と密接に関係しています。
従来のリプレースは「保守終了への対応」や「物理機器の入れ替え」が中心でしたが、現在ではクラウドシフトや仮想化、ゼロトラスト環境の構築、業務プロセスとの連携改善といった視点での“全体最適”を志向するケースが増えています。単なる入れ替えにとどまらず、将来を見据えた戦略的導入として位置付けられるようになっています。
リプレース(リプレイス)とマイグレーションの違い
「リプレース」とよく似た言葉に「マイグレーション(移行)」がありますが、この2つは目的やスコープ、進め方において異なる意味を持ちます。
リプレースは、ハードウェアやシステム構成、あるいはインフラ全体を“新しいものに置き換える”ことを指すのに対し、マイグレーションは、既存のデータやアプリケーションを“異なる環境へ移し替える”ことに主眼があります。たとえば、オンプレミス環境からクラウド環境へ業務アプリケーションを移行する場合、それはマイグレーションに該当します。
一方で、マイグレーションではソフトウェアやデータ構造をできるだけそのまま活かすのが基本となるため、現状維持を前提とした変化の少ない対応になります。リプレースはこれとは対照的に、最新技術や構成、運用方法を取り入れることで、性能や機能、セキュリティ面での改善や最適化を実現するための“刷新”を伴う選択です。
したがって、マイグレーションは既存資産を活かした「移行」、リプレースは新たな価値を見据えた「刷新」と整理すると違いが明確になります。両者の違いを理解したうえで、どちらが自社にとって適切なアプローチかを見極めることが、IT戦略の成功において重要な判断軸となります。
リプレース(リプレイス)の目的
リプレースは単なるハードウェアの更新にとどまらず、企業のIT戦略全体を支える重要な施策です。ここでは、多くの企業がリプレースを検討・実施する際に重視する代表的な目的をご紹介します。
メーカー保守のサポート終了に対応するため
メーカー保守の終了は、企業がリプレースを検討する大きなきっかけの一つです。メーカー保守が受けられなくなると、障害発生時の迅速な対応が困難になり、業務停止リスクが高まります。特に基幹システムやミッションクリティカルなインフラでは、万一のトラブルが事業全体に深刻な影響を与える可能性があります。
また、メーカーによる修正パッチやセキュリティアップデートの提供も終了するため、外部からの攻撃や内部不具合への脆弱性が増大します。こうした背景から、多くの企業はリスクの拡大を避けるため、計画的にリプレースを実施し、安定稼働と将来の業務拡張に備えたIT基盤の再構築を図ります。
IT資産の最適化
業務内容の変化や部門統合、DX化の進展により、以前は必要だった高スペックなサーバーやストレージが過剰になっているケースもあります。また、遊休化した機器がデータセンターのスペースや電源を圧迫している場合も多く、現状に合った構成へ見直すことで運用効率とコストの両面で改善が見込めます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)推進
ビジネス環境の変化に対応するには、AIやIoT、クラウドといった新技術への対応が求められます。旧来のハードウェアやソフトウェアでは、これらの技術を活用する足かせになることも。リプレースを通じて、柔軟性のあるIT基盤を整えることが、業務の高度化やデータ活用による意思決定の迅速化、ひいては競争力の強化につながります。
こうした目的を明確にすることで、単なる更新作業ではなく、将来を見据えたIT投資としてのリプレース戦略を立てることが可能になります。
なぜリプレース(リプレイス)はすぐにできないのか?

多くの企業が「必要性は理解しているが、すぐには動けない」というジレンマを抱えています。リプレースの重要性は認識しているものの、現実には踏み出せないというケースが非常に多く、その背景には複数の要因が複雑に絡み合っています。特に情シス部門では、限られた人員と予算の中で日々の運用を回している中、突発的な機器入れ替えや大規模な移行プロジェクトに着手する余力がないという事情が存在します。
また、単なるIT投資としてだけでなく、業務全体への影響を慎重に見極める必要があるため、移行判断には経営層との連携や現場理解が欠かせません。ここでは、企業がリプレースに踏み切れない主な理由について詳しく見ていきます。ただし、こうした課題は多くの企業が共通して抱えるものですが、それぞれに対応策があり、近年ではサポートサービスや柔軟な移行手法の活用によって、段階的に解決することも可能であることを念頭においてください。
年度内の予算が確保できていない
>突発的な機器の入れ替えは、当初の年度予算に計上されていないケースが大半であり、想定外の支出として捉えられます。特に中小企業や予算枠が厳格な組織では、予備費や緊急対応資金の確保が難しく、結果的に対応を先延ばしにせざるを得ない状況に追い込まれがちです。そのため、保守切れの状態が長期化し、機器の故障リスクと隣り合わせで業務を継続するという不安定な運用を余儀なくされることもあります。
稟議や調整に時間がかかる
リプレースは多くの場合、一定額以上の設備投資を伴うため、社内での稟議承認プロセスを経る必要があります。このプロセスでは、経理・総務・経営層など複数部門との調整が求められ、承認までに数週間〜数ヶ月かかるケースも少なくありません。また、導入機器の選定や比較検討を行う調査・資料作成にも工数がかかるため、スムーズな実行には時間的猶予と社内連携が欠かせません。
業務への影響が見えない(移行リスク)
新システムへの切り替えによって、既存業務にどのような影響が出るのかを正確に予測することは難しい場合があります。特に、業務フローが複雑で複数部署にまたがる場合や、基幹業務と密接に連携しているシステムをリプレースする際は、移行時のトラブルが現場全体に波及するリスクが伴います。また、操作性の変化による現場の混乱や一時的な生産性の低下も懸念されるため、業務影響を見極めた上での段階的移行やパイロット導入の検討が求められます。
既存システムとの互換性が不明確
新たに導入するシステムや機器が、現在稼働中のアプリケーションや周辺機器と正しく連携できるかどうかは、事前に十分な検証が必要です。特に、自社独自にカスタマイズされたシステムや古いミドルウェアを使用している場合、互換性の問題が発生しやすく、予期せぬエラーや業務停止の原因になりかねません。また、ベンダー間での仕様の差異により、一部機能が使えなくなるなどのトラブルも起こり得ます。互換性の担保には、導入前のPoC(概念実証)やテスト環境の活用が有効です。
インフラ全体に手を入れる余力がない
サーバーやストレージといった一部の機器だけでなく、ネットワーク機器、電源装置、セキュリティ機器などを含めたITインフラ全体を見直すとなると、膨大なコストと工数が発生します。また、複数部門が使用するシステムが複雑に絡み合っている場合、一部の変更が他のシステムに影響を及ぼす懸念もあります。そのため、情シス担当者が現場対応や日常業務に追われる中、インフラ全体に手を入れるプロジェクトを立ち上げる余力がないというケースが多く見られます。
リプレース(リプレイス)方式の種類とメリット・デメリット

リプレースの方式は、導入規模や移行リスク、運用方針に応じていくつかの選択肢に分かれます。以下に、代表的な4つの移行方式をご紹介します。
一括移行方式
一括移行方式とは、既存システムを完全に停止し、業務やサービスを一斉に新しい環境へ切り替える移行方法です。移行作業が一度で済むため、プロジェクト期間を短縮できる反面、トラブル時の業務影響が大きいため、慎重な判断が求められます。
一括移行方式のメリット
この方式の最大のメリットは、移行作業を短期間で完了できる点にあります。切り替え後は新システムへの統一が即座に実現するため、運用がシンプルになり、管理負荷の軽減にもつながります。また、旧システムとの並行稼働期間が不要になることで、二重管理やコスト増加といった問題も回避できます。
一括移行方式のデメリット
システムを一度に切り替えるという特性上、トラブル発生時のリスクは非常に高くなります。もし想定外の障害が発生した場合、全社的な業務停止につながる可能性があり、その影響は計り知れません。また、ユーザー教育やマニュアル整備、事前のリハーサルを含む入念な準備が不可欠であり、導入前の工数やストレスは相応に大きなものとなります。
段階移行方式
並行移行方式とは、旧システムと新システムを一定期間同時に稼働させながら、徐々に新システムへの利用を切り替えていく移行方法です。特に、システムが複数のモジュールに分かれている場合や、段階的な切り替えが求められる現場では、柔軟性と安全性の両立が図れる点で有効です。各モジュールの機能や業務影響を見極めながら段階的に切り替えることで、リスクを抑えつつ安定した運用移行が可能になります。
段階移行方式のメリット
段階的に進めることで、業務への影響を最小限に抑えながら新旧システムの移行が可能となります。一部の部門やサービスで先行導入してから、課題や改善点を抽出し、他部門の移行時に反映できるため、全体としての導入成功率が高まります。また、リソースの集中投入が不要なため、通常業務を維持しながらの移行が可能で、情シス部門の負担も分散されます。
段階移行方式のデメリット
段階的に進めることによって全体の移行期間が長期化する傾向があり、プロジェクトの完了までに想定以上の時間やコストがかかることがあります。また、移行期間中は新旧システムが混在する状態が続くため、データの整合性や運用フローの複雑化といった課題も発生しやすくなります。そのため、綿密な工程設計とマスターデータの一元管理が成功の鍵となります。
並行移行方式
並行移行方式とは、旧システムと新システムを一定期間同時に稼働させながら、徐々に新システムへの利用を切り替えていく移行方法です。移行の柔軟性と安全性を両立させたい場合に適しています。
並行移行方式のメリット
並行稼働により、移行後の不具合や想定外の問題が発生した際でも旧システムに戻すことができるため、業務へのリスクを大きく軽減できます。現場の業務フローやユーザーの慣れに応じて段階的な適応が可能であり、教育・トレーニング期間を設けながら円滑に運用を移行できる点も魅力です。特に、重要業務が絡む大規模なシステム移行では、安全性を重視した選択肢として高い評価を受けています。
並行移行方式のデメリット
旧システムと新システムを同時に運用する期間中は、データの整合性を保つための同期作業や管理工数が増加します。また、二重運用による一時的なコストの増大や、運用ルールの煩雑化も課題となりがちです。さらに、並行期間が長引くほど、ユーザーの混乱やシステム間の不整合が発生するリスクが高まるため、スケジュールと役割分担を明確にした計画的な実施が求められます。
パイロット方式
パイロット方式とは、特定の業務領域や拠点に限定して新システムを先行導入・検証し、その結果をもとに全社展開するかどうかを判断する移行手法です。段階移行や一括移行の前に、実地テストを通じて現場での適合性や問題点を明らかにすることを目的としています。
パイロット方式のメリット
パイロット方式の最大の利点は、実際の運用環境に近い状態でシステムの検証ができる点にあります。小規模であっても実務に沿った形で課題を洗い出せるため、全社展開前に重大な不具合や想定外の問題点に気づくことができます。これにより、システムの改善や導入計画の最適化が可能となり、失敗のリスクを大幅に軽減できます。また、先行導入した部門からのフィードバックを活かしながら、ユーザー教育やマニュアルのブラッシュアップも行えるため、全体移行時の混乱を抑える効果も期待できます。
パイロット方式のデメリット
パイロット導入には時間とリソースが追加で必要になる点が課題です。先行導入に伴う設定・検証・評価プロセスには一定の手間がかかり、スケジュール全体の長期化につながることがあります。また、パイロット実施箇所と他部門での業務要件が異なる場合、得られた成果や教訓をそのまま全体に適用できない可能性もあります。さらに、先行導入の結果が芳しくなかった場合には、全体計画の見直しが発生し、再設計や予算修正が必要になるリスクも考慮する必要があります。
どの方式が最適かは、システムの規模や業務特性、社内の体制によって異なります。自社にとってのリスクとリソースを天秤にかけ、柔軟に選定しましょう。
リプレース(リプレイス)を進める5つのステップ

実際にリプレースを進める際には、業務への影響を最小限に抑えつつ、確実な移行を実現するための入念な準備と段階的な計画が求められます。特に、初期段階における要件定義は非常に重要で、関係者間で認識のズレが生じないよう、目的や業務要件、対象機器、導入後の運用イメージなどを明文化しておく必要があります。多くの企業では、ハードウェアの選定や導入手配だけでなく、システム間の連携や業務フローの整理、ユーザー教育、リスクマネジメントなど、あらゆる側面を慎重に検討しながら進める必要があります。また、リプレースは一度きりのイベントではなく、その後の運用や保守体制の見直しにも関わる、長期的な視点を要する取り組みです。
そのため、以下に紹介する5つのステップを踏まえて、技術的・組織的な観点から計画的に進行していくことが成功の鍵となります。
現状機器の棚卸しと稼働状況の可視化
どの機器がEOSLを迎えているのか、または近く迎える予定なのかを明確にし、それらがどの業務プロセスやシステムに紐づいているかを整理します。あわせて、重要度や障害発生時の影響度を見極めることで、リプレースや延命対応の優先順位を判断するための基礎データとなります。ここでも、正確な要件定義が欠かせません。対象機器が担う業務やシステムの位置づけを正しく把握し、必要な可用性や性能要件を洗い出すことで、後工程の選定精度が高まります。
リプレースの目的と優先順位の整理
リプレースに取り組む際は、「なぜ今リプレースが必要なのか」「どの課題を解決したいのか」といった目的を丁寧に整理することが重要です。たとえば、現行システムの性能が業務負荷に耐えられなくなっている場合は「性能改善」が主眼になりますし、保守契約費用の増大や老朽機器の修理コストが課題であれば「保守コスト削減」が優先されます。また、自然災害やサイバー攻撃への備えを強化するために「BCP(事業継続計画)の強化」を目的とする企業も少なくありません。こうした目的を明確にすることで、対象機器の優先順位や導入方式の選定がより具体化し、経営層との合意形成や稟議プロセスもスムーズに進めやすくなります。
方式の選定と費用試算
自社の業務要件やシステム構成、社内体制に照らし合わせて、最適なリプレース方式を選定します。ここでも事前の要件定義が成功の分岐点となります。たとえば、「現行と同等性能でよいのか」「今後の拡張性やBCP対応も加味すべきか」など、要件をどう捉えるかによって導入方式や製品選定の方向性は大きく変わります。そのうえで、導入にかかる初期コスト・運用コスト・人的工数を具体的に算出し、スケジュールにかかる期間や業務停止の可能性、周辺システムへの影響範囲も含めて多角的に評価します。また、第三者保守との比較や段階的な切り替えなどの選択肢も視野に入れることで、より現実的かつ納得感のある判断につながります。
導入スケジュールとテスト環境の設計
移行プロジェクトの成功には、業務カレンダーや稼働ピークを考慮した無理のないスケジューリングが欠かせません。さらに、実際の運用環境に近いテスト環境を用いた事前検証を徹底することで、設定ミスや想定外のエラーを未然に防ぐことができます。これにより、ダウンタイムの発生リスクを最小限に抑えるだけでなく、業務影響やユーザーの混乱も回避しやすくなります。特に、基幹業務を支えるシステムの移行では、段階的な移行計画とリハーサルを繰り返すことで、スムーズな本番切り替えを実現することが重要です。
稼働後の運用体制の構築
リプレース後の安定運用を支えるためには、継続的な保守体制の整備が欠かせません。まず、機器やシステムに適した保守ベンダーを選定し、保守範囲や対応レベル、対応時間を明確にしたSLA(サービスレベルアグリーメント)を策定することが重要です。また、障害発生時に迅速かつ的確に対応できるよう、社内外の連携体制やエスカレーションルート、初動対応の手順書なども整備しておく必要があります。あわせて、運用開始後の評価・改善を見据えた新たな要件定義(フェーズ2以降)を行うことで、長期的な安定稼働と改善サイクルの継続が可能になります。加えて、定期的な点検やリモート監視体制の導入、ログ管理の自動化など、予防保全の観点も含めた総合的な運用管理を設計することが、長期的な安定稼働の鍵となります。
第三者保守という選択肢もある

「今すぐリプレースは難しいが、保守の不安を解消したい」——そんなときの現実的な選択肢が「第三者保守(TPM)」です。第三者保守とはメーカー以外の専門ベンダーが提供する保守サービスで、EOSL機器でも継続して利用することが可能になります。第三者保守の特徴やメリットは、以下のとおりです。
メーカー保守よりもコストを抑えられる
メーカーが提供する保守サービスは、新製品の販売を前提とした契約体系が多く、EOSL機器に対するサポートは割高になる傾向があります。一方、第三者保守は保守対象の機器や対応内容を絞り込んだ契約が可能なため、コスト効率のよい運用が実現できます。
メーカーで対応不可な保守も第三者保守なら継続可能
メーカー保守では、製造終了から年数が経過した機器について、修理パーツの確保が困難になったり、維持コストの観点から延長保守が提供されないケースがあります。一方、第三者保守では独自の部品調達網や在庫体制を活用し、メーカーが保守終了した機器にも対応可能です。これにより、現行システムを長期にわたり安定運用できるという大きなメリットがあります。
後ろのEOSLに合わせてシステム全体を延命できる
複数の異なる機器で構成されるシステムでは、メーカー保守だと機器ごとに保守終了時期(EOSL)が異なるため、管理が煩雑になります。第三者保守を利用すれば、すべての機器を後ろのEOSLに合わせて保守期間を合わせられるため、システム全体の寿命を延ばしつつ、計画的な運用が可能になります。
必要な範囲だけ契約できる
第三者保守では、保守対象の機器やサービスレベルを必要最小限に設定できるため、自社の状況に応じた最適な保守体制を構築できます。たとえば、全体ではなく一部拠点や機器に限定して保守を受けるといった運用も可能です。また、数カ月単位での契約も可能なことが多く、短期の利用や移行期間中のつなぎとしても柔軟に対応できます。
国内在庫や技術者により迅速に対応してもらえる
一部の第三者保守ベンダーは、自社で部品を在庫し、国内に技術拠点を設けているため、障害時には迅速な対応が可能です。これにより、ダウンタイムの最小化や業務影響の軽減が期待できます。
第三者保守とリプレース、どう使い分ける?
今期にリプレースを行うのか、第三者保守を入れて来季以降にリプレースを行うのか、どちらを選べばよいか迷う担当者の方も多いでしょう。リプレースと第三者保守のどちらを選ぶべきかは、自社のIT資産の状況や、直面している課題、そして今後の経営・システム戦略によって大きく変わってきます。たとえば、「今後数年間は安定稼働を維持できればよい」という短中期的な安定運用が主目的の企業にとっては、第三者保守による延命措置が最適です。一方で、「最新技術への対応」「セキュリティ強化」「業務効率化」など、IT基盤の刷新によって長期的な成長や変革を目指す企業にとっては、リプレースの方が適しているでしょう。
このように、目的や投資可能なリソース、業務の重要度によって選択肢は異なります。判断材料として、以下のような要素が比較の基準となります。
| 観点 | リプレース | 第三者保守 |
|---|---|---|
| 導入コスト | 高い | システム変更がないため不要 |
| 実行スピード | 年単位 | 2ヶ月程度 |
| システム更新 | あり(刷新) | なし(継続) |
| 技術的負荷 | 高い | 低い |
中長期的なIT戦略に沿ってシステムを刷新したい場合はリプレース。数年以内に更新予定があるが、今は動けないなら第三者保守。——このように併用・段階運用も選択肢になります。
まとめ:いま本当に必要なのは「最適な判断」
リプレースは、単なる“入れ替え”ではなく、事業継続・成長を支えるための重要な判断です。一方で、予算・人材・稟議など現場の制約も無視できません。
だからこそ、「今やるべきか」「今ではないが備えるべきか」という観点から最適解を探る必要があります。第三者保守のような柔軟な選択肢を活用しながら、自社の状況に合った対応を選びましょう。
ゲットイットでは、EOSLを迎えたIT機器の保守・延命・買取り(ITAD)まで一貫してご支援しています。ぜひ一度ご相談ください。



