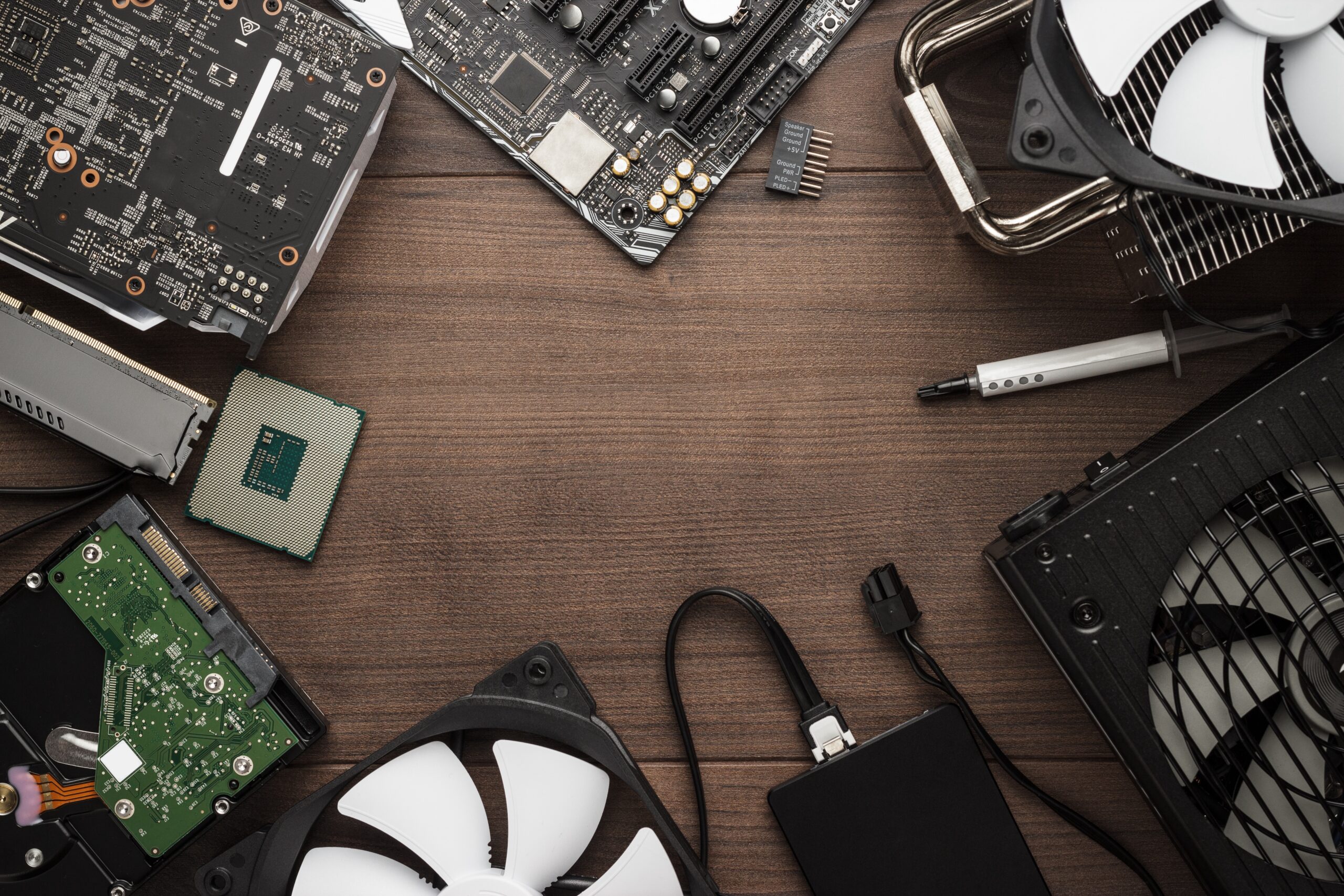
企業システムのクラウド移行やDX推進が進む中で、「マイグレーション(Migration)」という言葉を耳にする機会が増えています。マイグレーションは、業務の効率化やセキュリティ強化を実現するうえで欠かせない取り組みであり、システムの刷新や基盤再構築を行う際に検討されます。
しかし、マイグレーションと一口にいっても、その種類や手法は多岐にわたり、誤った理解のまま進めると、データ損失や運用停止といったリスクにもつながります。本記事では、マイグレーションの意味、代表的な種類や手法、成功させるためのポイントを体系的に解説します。これからマイグレーションを検討している担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
マイグレーションとは

まずは、マイグレーションの基本的な意味について解説します。
マイグレーションの定義と目的
マイグレーションとは、既存のシステム・データ・アプリケーションなどを、新しい環境へ安全に移行するプロセスを指します。単なる引っ越し作業ではなく、パフォーマンス向上や保守性の改善、セキュリティ強化といった目的を同時に遂行する点が特徴です。
たとえば、オンプレミス環境からクラウドへの移行や、古いOS・データベースから最新のものへの更新などもマイグレーションの一種です。特に、古いシステムを使い続けることで生じるリスクへの対策として、企業では計画的なマイグレーションが進められることが多いです。マイグレーションにより、業務の継続性を確保しつつ、将来的な技術革新にも柔軟に対応できる体制を整えることができます。
間違えやすいマイグレーション関連用語との違い
マイグレーションと混同されやすい用語には、コンバージョン、リプレース、モダナイゼーションなどがあります。ここでは、それぞれの意味と違いを整理し、誤用を防ぐポイントを解説します。
コンバージョンとマイグレーションの違い
コンバージョン(Conversion)は、主にデータ形式やファイル形式を変換する作業を指します。たとえば、CSVデータをデータベースに取り込む際のフォーマット変換などが該当します。マイグレーションと言葉の響きが似ており、移行と変換という意味においても誤解されやすい点が混同の原因です。
リプレースとマイグレーションの違い
リプレース(Replace)は、既存システムを新しいハードウェアやソフトウェアに置き換える行為を指します。マイグレーションが「移す」ことであるのに対し、リプレースは「入れ替える」ニュアンスが強い点が特徴です。またリプレースは、システムの土台を変更する場合に使われることが多く、単なるデータ移行よりも物理的な更新に焦点を当てることが多いです。
モダナイゼーション(Modernization)との違い
モダナイゼーションは、既存のシステムやアプリケーションを最新技術に対応させて再構築する取り組みです。マイグレーションが「移行」を指すのに対し、モダナイゼーションはより広い概念で、「クラウド化」「再設計」「業務最適化」などを含みます。
つまり、マイグレーションはモダナイゼーションの一部に位置づけられるケースが多く、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の手段としても活用されます。
マイグレーションが必要とされる理由

ここでは、なぜマイグレーションを行う必要が発生するのか、その背景と目的を具体的に解説します。
ランニングコストの削減
マイグレーションの大きな目的のひとつが、運用コストの最適化です。老朽化したシステムは保守費用が高騰し、開発ベンダーのサポート終了などによって維持が難しくなります。
そこで、マイグレーションによりクラウド環境や仮想化インフラへ移行することで、サーバ運用・保守コストを抑え、リソースを柔軟に拡張できるようになります。また、マイグレーションを行うことで不要なハードウェア投資を避けられるため、固定費の削減にもつながります。
セキュリティ向上と故障リスクの回避
古いシステムを長年利用していると、セキュリティ更新が追いつかず、脆弱性によるリスクが高まります。
マイグレーションは脆弱性によるリスクを解消するためにも行われ、マイグレーションを行うことで最新のセキュリティ基盤を備えた環境へ移行でき、サイバー攻撃やデータ漏えいのリスクを軽減できます。また、クラウド環境ではバックアップや冗長化が標準で実装されており、システム障害時の復旧も迅速です。ハードウェアの老朽化に伴うダウンタイムを回避し、安定稼働を維持するうえでも、マイグレーションは極めて有効な手段といえるでしょう。
ブラックボックス化の防止
長年運用されてきたレガシーシステムでは、ドキュメントが整理されておらず、開発者が退職すると構造が把握できない「ブラックボックス化」が発生します。こうした状態では、機能追加や不具合修正のたびにリスクが伴い、柔軟な事業運営を行うことが難しくなります。
このような状況も、マイグレーションが解決の選択肢となります。マイグレーションを通じて最新環境へ移行し、ソースコードや設計情報を再整備することで、属人的な依存を解消できます。結果として、運用体制の透明性が高まり、組織全体でシステムを継続的に改善できる体制が整うのです。
成長戦略の一環としての再構築
マイグレーションは、単なる現状維持のための施策ではなく、企業の成長を支える再構築プロセスでもあります。新しい技術基盤を採用することで、AI・IoT・データ分析などの先端テクノロジーを活用しやすくなり、事業拡大のスピードを高められます。古いシステムを維持するコストよりも、最新環境への移行が中長期的な競争力を生むケースが増えています。特に経営層にとって、マイグレーションは「守りのIT」から「攻めのIT」への転換点となる重要な意思決定といえるでしょう。
対象の違いによるマイグレーションの種類

マイグレーションには、対象や方法に応じていくつかの種類があります。ここでは、代表的なマイグレーションの分類を紹介し、それぞれの特徴と実施目的を解説します。
データマイグレーション
データマイグレーションは、データベースやストレージなどに保管された情報を、新しい環境に移行するプロセスです。企業の業務データや顧客情報など、事業運営に欠かせない情報資産を、正確かつ安全に移すことが目的となります。
たとえば、オンプレミスのデータベースをクラウド上のRDBへ移行するケースや、旧バージョンのDBMSから新バージョンへの移行が該当します。移行時にはデータの整合性や欠損チェック、暗号化設定の再確認などが求められます。システム全体の中でも特に慎重な手順が必要な工程であり、専門的な知識とテスト環境の構築が成功の鍵を握ります。
サーバーマイグレーション
サーバーマイグレーションは、物理サーバや仮想サーバの稼働環境を別の基盤へ移すことを指します。古いサーバを新しいハードウェアに置き換える場合や、データセンターからクラウドへ移行するケースが一般的です。
特に近年では、クラウドサービスの発展により、AWSやAzureなどのIaaS環境への移行が主流になっています。これにより、スケーラビリティや可用性を高め、障害時のリカバリーも容易になります。また、サーバーマイグレーションはインフラの近代化だけでなく、セキュリティやバックアップ体制の強化にもつながります。
レガシーマイグレーション
レガシーマイグレーションとは、長期間稼働している古いシステム(レガシーシステム)を、最新の技術基盤へ移行する取り組みです。老朽化した言語やOS、ハードウェアに依存しているシステムを現代のアーキテクチャに再構築することで、保守性・柔軟性を向上させます。
多くの企業では、古いプログラムがブラックボックス化し、修正が困難になる課題を抱えています。レガシーマイグレーションを実施することで、ソースコードを整理し、ドキュメント化を進め、今後の機能拡張にも対応できる基盤を確立できます。単なる更新ではなく、業務改革と技術革新を両立するプロジェクトとして位置づけられています。
アプリケーションマイグレーション
アプリケーションマイグレーションは、企業が利用している業務アプリケーションを新しいプラットフォームに移行する作業です。代表例として、オンプレミスで運用していた販売管理や人事システムをクラウドサービス上に移行するケースが挙げられます。
この移行により、アプリの拡張性や可用性が向上し、リモート環境からの利用や自動アップデートも可能になります。また、クラウドネイティブな環境では、マイクロサービスやAPI連携を活用することで業務プロセスを柔軟に設計できます。アプリケーションマイグレーションは、DX推進の中核を担うステップとして、多くの企業が優先的に取り組む領域です。
ライブマイグレーション(無停止移行)
ライブマイグレーションは、稼働中の仮想マシンを停止させずに別のホストサーバへ移行する技術です。業務システムを止めずにインフラを更新できるため、24時間稼働が求められる金融・医療・製造業などで特に重視されています。
移行中のメモリ状態や実行プロセスをリアルタイムで複製し、移行先のサーバへシームレスに切り替えることで、ユーザーに影響を与えません。これにより、メンテナンス時のダウンタイムをゼロに近づけることが可能です。ただし、ネットワーク帯域やストレージ速度の確保など、事前準備には高い技術要件が求められます。
クイックマイグレーション
クイックマイグレーションは、一時的に仮想マシンを停止しながら短時間で別ホストへ移行する手法です。ライブマイグレーションほどの連続性はありませんが、作業コストが低く、システムの負荷を抑えながら効率的に移行できる点が特徴です。
比較的小規模なシステムや夜間メンテナンスの時間を確保できる場合に適しており、スピード重視の環境で採用されることが多い手法です。ダウンタイムを最小限に抑えつつ、安全かつ確実にサーバを切り替えられる点から、仮想環境運用の現場では広く活用されています。
マイグレーションの手法

ここではマイグレーションの代表的な5つの手法を紹介し、それぞれの特徴と適用シーンを解説します。
リホスト
リホストとは、既存のシステムやアプリケーションをほぼそのまま新しいインフラへ移行する方法です。システム構造やアプリのコードを大きく変更せず、物理サーバからクラウドや仮想環境に「持ち上げて移す」イメージで行います。
この手法のメリットは、短期間で移行できる点と、初期費用を抑えやすい点にあります。一方で、旧環境の課題をそのまま引き継ぐリスクもあるため、移行後に最適化を行うことが望まれます。既存システムの改修リソースが限られている企業や、まずはスピーディにクラウドへ移行したい場合に適した手法です。
リプラットフォーム(リライト)
リプラットフォームは、既存のシステムを新しいプラットフォーム上に移行しながら、一部の構成や設定を最適化する方法です。たとえば、アプリをクラウド環境に合わせてコンテナ化したり、データベースをマネージドサービスに置き換えるなどが挙げられます。
リホストと比べて多少の改修が発生しますが、システム全体を作り直す必要はありません。コストと効果のバランスが良く、最も採用されることの多い手法です。
また、アプリケーションコードを現行仕様に合わせて書き直す「リライト」も、リプラットフォームの一種と考えられます。新環境の性能を活かしつつ、既存システムの資産を最大限活用できるのが特徴です。
リビルド
リビルドは、既存のシステムをゼロから再構築する方法です。アーキテクチャ設計を一新し、最新の開発言語やフレームワークを採用することで、性能・保守性・拡張性を大幅に高められます。
クラウドネイティブ開発やマイクロサービス化を前提とする場合、このリビルドが選ばれることが多いです。初期コストや開発期間は長くなりますが、長期的な運用効率を考えると、結果的に最も高い効果を発揮するケースもよく見られます。
特にレガシー環境が業務の足かせとなっている企業や、新しい事業モデルに対応する必要がある企業にとって、リビルドは「攻めのマイグレーション」といえるでしょう。
リファクタリング
リファクタリングは、システム全体を再構築するのではなく、ソースコードの構造を整理・改善する手法です。プログラムの動作は変えずに、可読性や保守性を向上させることを目的としています。
たとえば、重複したコードを統合したり、無駄な処理を削除したりすることで、将来的な改修コストを大幅に削減できます。大規模なマイグレーションを行う前に、まずリファクタリングで内部品質を整えるケースも多く見られます。結果として、移行後の運用が安定し、バグ発生率の低下にもつながります。
SaaS移行・ラッピング
SaaS移行とは、既存のシステム機能を外部のクラウドサービス(SaaS)に置き換える手法です。自社で保守する必要がなくなり、利用料のみで最新機能を活用できます。たとえば、社内メールシステムをMicrosoft 365やGoogle Workspaceに切り替えるケースなどが該当します。
一方、ラッピングは旧システムを残したまま、新しいアプリケーションやAPIを「外側からかぶせる」ように連携させる方法です。これにより、レガシー環境を維持しながら段階的にモダナイズを進められます。大規模刷新が難しい環境でも、現実的な改善策として有効なアプローチです。
マイグレーションの流れ・工程

ここでは、一般的なマイグレーションの進め方を5つの工程に分けて解説します。各ステップでの目的と注意点を押さえることで、失敗のない移行を実現できます。
現行システムの調査・課題把握
最初のステップは、現行システムの全体像を正確に把握することです。サーバ構成、ネットワーク設定、データベースの依存関係、業務アプリや不要機能を徹底的に洗い出し、システムの整理も行います。
この段階で課題を見落とすと、後工程でのトラブルやコスト増大につながるため、関係部門を巻き込みながら詳細なヒアリングを行うことが重要です。また、どのシステムが事業の中核を担っているのかを特定し、優先順位をつけておくことで、計画段階の精度が高まります。
方針決定と移行計画の策定
現状把握が完了したら、次に移行方針とスケジュールを決定します。ここでは、「どの範囲を移行するか」「どの手法を用いるか」「どの時期に実施するか」を明確化します。
クラウド移行や仮想化などの技術選定を行う際は、費用対効果やセキュリティポリシーも考慮する必要があります。また、移行対象を段階的に分ける「フェーズ型計画」を採用すると、リスクを最小限に抑えながら進められます。
さらに、ベンダー選定や人員配置を含めたリソース計画も同時に行うことで、プロジェクト全体の見通しを立てやすくなります。
PoC(実証実験)とリハーサル
本番移行に入る前に、小規模で実際の移行をテストする「PoC(Proof of Concept)」を実施します。PoCでは、想定どおりにデータが移行できるか、システム連携に問題がないか、パフォーマンスが維持されるかを確認します。
この検証結果をもとに、設定変更や移行手順の改善を行い、問題点を洗い出すことが重要です。その後、本番環境を想定したリハーサルを実施し、障害発生時のリカバリ手順やロールバック計画も確認します。
このフェーズを丁寧に行うことで、実運用時のリスクを大幅に軽減できます。PoCとリハーサルは、マイグレーションの「安全装置」といえる工程です。
本番移行と検証
準備が整ったら、いよいよ本番環境での移行を行います。移行の実施時には、業務への影響を最小化するため、夜間や休日などシステム利用が少ない時間帯を選定するのが一般的です。
移行後は、データの整合性、アプリケーションの稼働状況、ユーザーアクセスの安定性などを詳細に検証します。検証が不十分なまま運用を開始すると、予期せぬエラーが顧客対応や業務に支障をきたす可能性があります。
そのため、テスト項目を事前に明確化し、チェックリストに基づいて実施することが求められます。安定稼働が確認できた段階で、正式な切り替えが完了となります。
運用・改善
マイグレーションは移行完了で終わりではありません。移行後の運用フェーズで、監視・チューニング・改善を継続的に行うことが大切です。
新環境の稼働状況をモニタリングし、パフォーマンスの最適化やセキュリティ更新を行います。また、業務部門からのフィードバックを反映し、運用プロセスを改善していくことも重要です。
さらに近年注目されているのが「継続的マイグレーション(Continuous Migration)」という考え方です。これは、一度の大規模移行で完了させるのではなく、技術の進化やビジネス変化に合わせて段階的・継続的にシステムを最適化していくアプローチを指します。
環境を定期的に見直し、小規模なアップデートを重ねることで、システムの陳腐化を防ぎ、常に最新の状態を維持できます。安定稼働と継続改善を両立することで、移行の成果を最大限に引き出せます。
マイグレーションを成功させるポイントと注意点

ここでは、移行を安全かつ効果的に進めるための5つの重要ポイントを紹介します。
下準備と関係者間の連携を徹底する
成功するマイグレーションの第一歩は、徹底した準備と情報共有にあります。現行システムの仕様やデータ構造を正確に把握し、影響範囲を明確にすることが重要です。特に、業務部門・IT部門・外部ベンダー間で認識のズレがあると、移行時にトラブルが発生しやすくなります。
そのため、初期段階で「どのデータを、いつ、どのように移行するか」を明文化した移行計画書を作成し、関係者全員で共有することが不可欠です。加えて、連絡経路や意思決定フローを明確にしておくことで、問題発生時の対応速度を大幅に高めることができます。
自社に適した移行先を選定する
移行先の選定は、マイグレーションの成否を左右する重要な要素です。クラウド・オンプレミス・ハイブリッドなどの選択肢を比較し、自社のセキュリティ要件や運用コストに最も適した環境を選びましょう。
余裕をもったスケジュールを設定する
また、移行スケジュールは余裕を持って設定することが望ましいです。リソース不足や想定外の障害が発生した場合に備え、リカバリー期間を確保しておくと安心です。さらに、段階的な移行(フェーズ移行)を採用することで、業務影響を抑えながら進めることができます。計画と実行を並行して調整できる柔軟性が、プロジェクトの成功に直結します。
テストとリスク対策を重視する
マイグレーションでは、データの欠損やアプリケーションの動作不良など、さまざまなリスクが想定されます。そのため、テスト工程を軽視してはいけません。
特に重要なのが、段階的テストとリハーサルテストの実施です。まずは一部データでテスト移行を行い、問題がなければ全体へと拡大する方法が効果的です。また、障害発生時に元の環境へ戻すロールバック手順を用意しておくことも必須です。さらに、データバックアップを複数箇所に確保しておくことで、万一のトラブルにも迅速に対応できます。テストとリスク対策は、マイグレーションを安全に完遂するための「保険」といえるでしょう。
外部ベンダーや専門サービスの活用も検討する
マイグレーションには高度な技術と経験が必要です。社内リソースだけで対応が難しい場合は、専門の外部ベンダーやマイグレーション支援サービスを活用するのが効果的です。
専門ベンダーは、既存環境の診断から設計・移行・運用までを一貫してサポートできるため、作業負荷を大幅に軽減できます。また、クラウドベンダーが提供するツールやテンプレートを利用すれば、コストを抑えつつ安全に移行を進めることが可能です。特に、複雑なシステム間連携や大規模データの移行では、専門知識を持つパートナーとの協働が成功への近道となります。
第三者保守を活用した移行コストの最適化を模索する
マイグレーションを進める際、すぐに全システムを移行できないケースも少なくありません。そうした場合に有効なのが、第三者保守サービスの活用です。第三者保守とは、メーカーサポートが終了したハードウェアやソフトウェアを、専門の外部業者が独自に保守・修理・サポートするサービスを指します。これにより、現行システムを安全に延命しながら、段階的に新環境への移行を計画できます。
たとえば、旧サーバやストレージをすぐにクラウドへ移行できない場合でも、第三者保守を導入すれば安定運用を維持しつつ、更新コストを抑えられます。メーカー保守よりも料金が低いことが多く、「移行前のつなぎ期間を最小コストで維持できる」点が最大のメリットです。
また、ハードウェア障害のリスクを軽減しながら、テストや検証に十分な時間を確保できるため、無理のないスケジュールでマイグレーションを実施できます。第三者保守は、オンプレミス環境とクラウド環境を共存させながら移行を進めるハイブリッド型戦略を支える実践的な手段です。
まとめ
マイグレーションとは、単なるシステムの移行ではなく、企業の未来を見据えた基盤再構築のプロセスです。老朽化した環境を最新技術へ移行することで、コスト削減・セキュリティ強化・業務効率化など、複数の効果を得られます。
成功の鍵は、現状分析とシステムの整理、綿密な計画、そして関係者間の連携にあります。さらに、PoCやテストを通じてリスクを最小化し、移行後も継続的に改善を重ねることで、IT基盤の安定稼働を維持できます。また、すぐに全面移行が難しい場合には、第三者保守サービスを活用することも有効な選択肢です。現行システムを安全に延命しながら、段階的にクラウドや新環境へ移行することで、コストとリスクの両面を最適化できます。
ゲットイットでは、EOSLを迎えたIT機器の保守・延命・買取り(ITAD)まで一貫してご支援しています。ぜひ一度ご相談ください。



